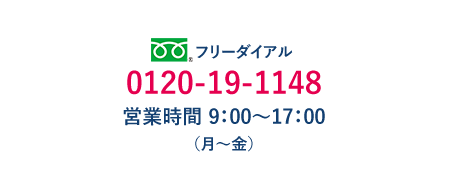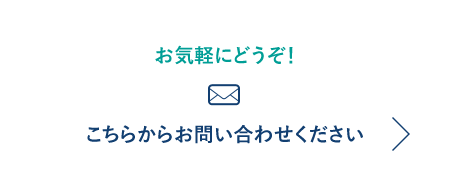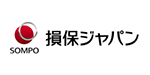ここのところ、
テレビで地震速報が流れる頻度が増えた気がします。
これって、私だけでしょうか?
まぁ、最近はテレビをあまり見なくなり、
YouTubeやサブスクリプションで映像を満喫される方も多いですよね。
今回は、保険の話ではなく、
気になったここ最近の地震について気象庁のデータを調べてみました。
1.最近の地震の傾向
2.地震の原因
3.「本震→余震型」、「前震→本震→余震型」など

1.最近の地震の傾向
気象庁のデータベース検索サイトから単純に5月だけの数値を拾いました。
(対象を震度3以上としました)
2020年5月⇒32回
2019年5月⇒16回
2018年5月⇒19回
さらに、
2010年5月⇒6回
2000年5月⇒5回
ざっくり10年毎になってますが、
これだけ並べると確かに昔より多くなったのかなぁ~
と感じますね。
(年間比較はしておりませんのでご了承ください)
2.地震の原因
こちらも気象庁のホームページが参考になります。
原因の主な要素は2つあるようで、
・プレート境界
・活断層
プレート境界は、
先般の「東日本大震災」や
今後懸念される「東南海地震」などが挙げられます。
例えばユーラシアプレートとフィリピン海プレートとのズレが
耐えられなくなり、プレートが跳ね上がることが原因です。
なので、一度起こると凄まじい威力となるそうです。
活断層の例としては、
「阪神淡路大震災」や「熊本地震」です。
陸域の浅い部分でのズレが原因で被害が起こります。
日々の地震の多くはこちらに該当するようですね。
規模も様々、、、です。
3.「本震→余震型」、「前震→本震→余震型」など
最後に、
私もよくわかっていませんでしたが、
地震の活動パターンには、
・「本震→余震型」
・「前震→本震→余震型」
・「群発型」
の3通りがあるようです。
ちなみに、私は群発型片頭痛かもしれません^^;
本震が最初に発生する場合、
地震の規模が大きいほど余震回数は多く、
収まるまでの期間も長くなるのが一般出来ですよね。
一方、
前震が本震に先立って起こる場合、
(今回のブログもこのケースを心配しているわけで)
小さな地震を何度も伴います。
多くの場合、際立った特徴がなく、
本震が発生してからその前震と判断されるそうです。
名前が怖いですが、
群発型は、規模の小さい地震が
連続的に激しくなったり、弱くなったりだらだらと
活動を繰り返すパターンが一般的だそうです。
さきほどのプレートや活断層が原因ではなく、
マグマが岩盤内へ貫入することによって、
発生していることが多いとのこと。
2000年の伊豆諸島群発地震などがそのタイプです。
こうやって地震についていろいろ
調べていくと防災グッズが気になり始めました(笑)
なので、
次回は防災グッズについてもいろいろリサーチしてみますね☆
【Facebook】
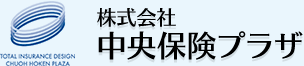
![[FREE DIAL]0120-19-1148 営業時間 9:00~17:00(月~金)](/img/common/tel.gif)